【コラムリレー08「博物館?資料のウラ側」第17回】
ミュージアムの表舞台飾るさまざまな展示物。そこには、普段表には見えない立ち入り禁止の知の迷宮の膨大な資料から作られた展示なのです。

ミュージアムのアイヌ文化の展示に、アイヌ文様が刺繍された衣装をよく見ますね。美術的で左右対称のシンメトリックで美しい衣装がよく展示されています。でも、アイヌの人たちは、みんな刺繍が上手だったんでしょうか?
ミュージアムで展示している衣装は、収蔵庫にある数多くの衣装の中から、美術的に美しく出来が良いものが展示されている場合も多いのです。また学芸員が資料収集の際、できるだけきれいで出来の良いものを収集していることも原因の一つだと思います。しかし寄贈されたりしたアイヌ衣装の中には、展示には出てこない、刺繍が縫いかけで終わってるものや、文様が全然左右対称になってないものも、沢山あるのです。上手じゃないアイヌ衣装の展示も見てみたいですね。
アイヌの人すべてが器用で刺繍が上手であるわけではないのです。器用な人も不器用な人もいる現代の人と同じです。多くの衣服を集めることで、アイヌ文様の意味や地域の違いが判るだけでなく、その当時の人々の暮らしや生き様も垣間見ることが出来るのです。そこを多く収蔵品の中から炙り出せている展示解説はワクワクします。
「ブラキストン線」というのを知っているでしょうか?北海道の生物相と本州の生物相の違いを表す生物境界線のことです。北海道にはニホンザル、モグラ科、ニホンカモシカ、ヤマネ、ムササビ、ニホンリス、ツキノワグマ、キジ、ヤマドリ、アオゲラ、エナガなどは生息してないですよね。反対に本州以南にはヒグマ、クロテン、ナキウサギ、エゾヤチネズミ、エゾリス、エゾシマリス、ヤマゲラ、エゾライチョウ、シマエナガは生息してません。
津軽海峡に動物分布の境界線があることに気がついたのが、イギリス出身の軍人・実業家・動物学者・貿易商・探検家のトーマス・ライト・ブレーキストン(Thomas Wright Blakiston)です。1883年のアジア協会報で発表し、地震学者ジョン・ミルンがこの生物境界をブラキストン線と名付けました。
ブラキストンは箱館(函館)に幕末から明治初期にかけて20年近く滞在し、北海道を始め千島や本州の鳥類調査を行い、多くの鳥の収集をしていたのです。
多くの標本を集める中で、北海道で集めた鳥類相と本州で集めた鳥類相が異なってる、ということに気がつき、始めて地域ごとの鳥の種構成の違いが見えてきた訳です。北海道と本州の間の生物境界を見つけたことにより、北海道や日本の生物相や日本列島の成り立ちをも明らかにするきっかけになりました。このブラキストン収集の鳥類標本は、現在北海道大学総合博物館(HUNHM) に収蔵されています。

ブラキストン線は哺乳類鳥類の分布境界。黒松内低地帯線はブナ林の北限、石狩亭地帯線は昆虫の分布境界、八田線は爬虫類の分布境界、シュミット線と宮部線は高木の分布境界、南樺太線は蝶の分布境界
展示室に並んでいる資料に名前が付けられているだけでは、それは古道具屋の店舗とあまり変わりません。ミュージアムは単に多くのモノを古道具屋のように集めているわけではありません。数少ない資料だけでは見えて来ず、多くのモノが集めることによって見えてくるものがあり、学芸員はその資料自身が物語る歴史や存在する意味を、展示解説として表体に出すことにあるです。展示解説の裏側にある、資料に隠れた秘密やそ面白さや不思議さを皆さんと共有することが、ミュージアムの醍醐味でもあるのです。

バックヤードに隠されている膨大な”知”の結晶、ミュージアムの本当の価値は裏側にある。バックヤードツアーの催しがあったら、ぜひ参加することをオススメします。展示の表舞台だけではわからない、ミュージアムの面白さや凄さを体感することが出来るでしょう。
フリーランスキュレーター 札幌大学 非常勤講師 斎藤和範
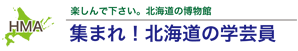 集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ
集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ





