【コラムリレー08 「博物館~資料のウラ側」第13回】
2025年は、戦後80年の節目の年です。皆さんは「墨塗り教科書」というワードを聞いたことがあるでしょうか。利尻富士町には、利尻小学校で使われた戦時中の教科書が30冊ほど残されており、その一部が利尻島郷土資料館に展示されています。
1941(昭和16)年4月に、小学校は軍国教育にシフトした国民学校に改組され、これまでの尋常科が初等科(6年間)となり、高等科は2年間としました。太平洋戦争の口火が切られたのは、この年の12月でした。
日本の敗戦後、戦時中に使用されていた教科書には、戦意高揚などを促す箇所があったことから、GHQの指令により、紙貼りや墨塗りなどによる部分的な削除が行なわれました。それを裏付ける資料が、郷土資料館の前身である鬼脇村役場(おにわきむらやくば)の公文書「教育雑件(昭和21年)」に綴られています。それは「国民学校後期使用図書中ノ削除修正箇所ノ件」という北海道庁公報で、基本的にはこの指示にもとづいて、教科書の削除修正が行われたようです。
では、実際に削除された内容を見てみましょう。

「初等科 国語 四(資料8167)」のうち 「三 バナナ」の墨塗り箇所は、
「台湾から神戸や、東京へ通ふ汽船といふ汽船は、いつもバナナを積んでいます」
「北海道や樺太はいふまでもなく、北支那から、北満州の雪の夜の家々にも行つて、みんなを喜ばしています」
で、戦争に関連した国や土地の名が消されました。

削除方法は、墨塗りにとどまらず「紙貼り」や「切り取り」などの方法もあります。
「初等科 国語 六(資料8172)」のうち「八 初冬二題 ゆず」の紙貼り箇所は、
「なつかしいゆずのかをり、わたしは、じつと梢を仰ぎ見た、今は部隊長になつて、戦地へ行つている をぢさんを思ひながら。」
こうした教科書の部分削除は、敗戦により教育方針が一変したことを物語っていますが、その裏で当時の教師は、どのような思いや葛藤を抱いていたのか。前出の資料8172は、紙貼りが丁寧であること、下記のようなメモが挟まっていたことから、教師用教科書と考えられています。

「我が国の教育界は、いわゆる英雄豪傑と称する者を標準とし、道徳なども平時の道徳よりもむしろ有事の道徳を鼓吹し、すべて非常な人物、非常な豪傑、何もかも非常非常を標準として、かかる人物を養成せねばならぬと考えて来た。是は大いなる誤謬であると思う。「アングロサクソン」の教育は、市民として堅固な品格を養成する事に重きを置き、学問よりも紳士なるの情操や礼儀作法に練達することに心を用い、一個の紳士として社会に立つも、敢て恥しくないように育て上げることである。我が国人ももはや島国民でなくして大国民なる資格を具備せねばならぬ時機となりし、故に非常人物・非常豪傑の標準とするをやめて通常な健全な平凡な人間を養うことに注意せねばならぬ。率先実行彼等に先だって進み、何事も自ら行うて模範を示し、口を以って命ずる前に身を挺して彼等を導き、彼等を尊重して、その自重心を養成せしめんか。(一部修正)」
文脈からは、戦時中の教育に疑問を持ちこれから将来ある彼等(子どもたち)を尊重し自分自身を重んじる心を養成しようとする決意や熱意を感じます。
時を同じくして、戦後の日本の健全な教育制度再建に必要な援助を目的とした米国教育使節団が訪れ、新たな教育指針が示されました。そのなかには現在にも通ずる内容がみられますので、皆さんもぜひ一読してみてください。
(利尻富士町教育委員会 山谷 文人)
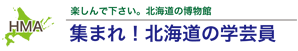 集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ
集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ







