「絵を展示しています」と言われてどのような光景を想像するでしょうか。多くの人が額縁に入った状態の絵が壁面に並んでいる光景を思い浮かべたと思います。有島記念館(以下、当館)でも同様です。
では作品を普段みなさんがご覧になる状態にするまでどのような道のりがあるのでしょうか。今回は当館で約1万点の作品を収蔵しているイラストレーター・藤倉英幸(ふじくら ひでゆき)のはり絵を例にご紹介します。
当館で収蔵している藤倉さんのはり絵は「収蔵庫」という温湿度管理がされた場所で保管しています。ほとんどの場合が厚さ2~3mmのイラストレーションボードという分厚い紙を土台にしており、そこに洋紙を切り貼りして風景などを描いています。美術館では絵画は額縁に入れた状態で収蔵庫の専用の壁に掛けていることが多いのですが、当館では専用の箱に大きさごとに分けて保管しています。なぜなら当館は25平米ほどの収蔵庫にはり絵約1万点に加え様々な資料を収蔵しています。そのため少しでもコンパクトにする必要があるのです。(写真1)(写真2)
保管する際は1箱あたり7作品前後になるようにしていますが約5kgになることも!箱も作品も紙でできているのですが、たかが紙、されど紙。身長160㎝ほどの筆者だと1度に持つのは多くても2箱が限界です。そんな作品をなんとか箱から出せました!では額縁に入れて壁に掛ければ終わり!とはならないのがさらに苦労するところ。
藤倉さんの作品はこのような状態で展示されています。(写真3)
中心にイラストがありその周囲は四角形の枠がついています。これはマットという白い紙製の枠のようなもので作品をより美しく見せたり、作品の表面を保護する役割があります。作品は鑑賞者側から見ると下の写真の順番で入っています。(写真4)
このマットがなかなかのくせ者。額縁やマットの枠の大きさ、マットの枠から見せる部分は藤倉さんの指定があります。それに合わせて展示したいのですが単純に前述した順番で入れるだけでは作家の意図した見え方にならない時があるのです。額縁やマットの大きさにぴったり合うように制作されていると思いきや一回り小さかったり、大きかったりするため作品の加工が必要となるのです。
この作業は藤倉さんと相談しながらどうすれば意図した見え方になるのか考えながら行います。この時に作品を1mm単位、場合によっては0,1mm単位で調整することもしばしば。この調整によって額縁の中で作品が動くことによる破損やそもそも入らないということを防ぎます。
さて、ここまできてようやく額縁に入れて壁に掛けるだけの状態になるのです!この作業は作品1点につき3時間かかることも。しかし、一度この加工をしてしまえば次回以降は額縁に入れるまで数十分で終わらせることができます。
現在は作家を知っている世代が作品に込める思いなどを聞いているので多少の苦労は惜しまずに作品の展示をしています。しかし作家のことを知らない世代に今後この作品が託されたときに「展示できる状態にするのが大変だから」と誰の目にも触れなくなってしまうのはとても悲しいこと。そうならないために最初は時間をかけてでもこういった作業をするのです。
今回は当館で収蔵するはり絵を例にあげてご紹介しました。みなさんが見る光景にたどり着くまでに様々な苦労があることを少しでも知っていただけたのではないでしょうか。当館に限らず展示ができあがるまで見えないところで学芸員は様々な苦労をしています。そんなところに少しだけ思いをはせて展示を見ていただけると嬉しいです。
(有島記念館 学芸員 河野紫杏)
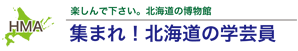 集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ
集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ









