コラムリレー08「博物館〜資料のウラ側」第2回
釧路市立博物館の展示室には「初秋のヤチボウズ」のレプリカがあります。
ヤチボウズは釧路地方の山の中の湿地や湿原などでよく見られる、カヤツリグサ科スゲ属の植物が株状に高く成長したものです。漢字では谷地坊主または野地坊主と書かれ、谷地=湿地にあって人の頭のような形をしていることから、こう呼ばれるようになったようです。
博物館のレプリカでは、ヤチボウズの上にミヤマアキノキリンソウ(コガネギク)、サワギキョウなど晩夏〜秋の花が咲いている様子が再現されていますが、野外では見ることができない地下の部分も作り込まれています。
上の写真は、1983年に現在の博物館の開館準備中に撮られた、設置前のレプリカの記録で、半球形の「土台」の部分の色が2色に分かれているのが分かります。色が濃いところはヤチボウズを作るカブスゲの根茎(地中の茎)、薄いところは土を表しているのですが、ここでちょっとした違和感。観察会でヤチボウズを切ってみたとき、中身は根茎がからまったものだったような……。
観察会で撮った写真(上)を見ると、ヤチボウズのサイズによって「中身」に違いがありました。写真左側の小さいヤチボウズ(高さ15~20cmくらい)は博物館の模型と同じように下部は主に土で上部は根茎ですが、右側のヤチボウズ(高さ30〜35cmくらい)は全体に根茎が目立ち、明らかに「土」という部分はありません。
もう1つ、高さ40cmほどのヤチボウズを半割にして乾燥させた標本を見ると、やはりヤチボウズの形は根茎が作っていることが分かります。
ヤチボウズは一般的に、密な株状になる根茎が分けつを繰り返すことと、冬季の土壌凍結で株ごと持ち上げられることの繰り返しで高く成長すると考えられていて、博物館の展示パネル(下図)でもそのように解説されています。パネルの図のヤチボウズの中身の色分けとジオラマのようすは一致しています。

観察会の写真からも分かるように、ヤチボウズの大きさによって中身のようすは違います。また、ヤチボウズを作るスゲは何種類かあり、スゲの種類によってヤチボウズの形や高さが異なります(慣れると形で見分けられるようになります)。釧路地方で一番ふつうに見られるのはカブスゲのヤチボウズですが、川沿いではタニガワスゲ、湖岸ではオオアゼスゲなど、違う種類が見られます。
ヤチボウズの成長速度について、1年に1cmと言われることもありますが、はっきりとは分かっていません。釧路湿原の調査では「10年間(1956〜1965)に高さの増大はいずれも1cm以下にとどまっていた」という報告もあります(田中1975)。きちんと計測していない野外観察の印象では、高さ10cmくらいの低い状態を長年維持している個体もあるようです。成長段階や環境によって成長速度が異なるものと考えられ、調査をしてみたいと思っています。
ヤチボウズについては分かっていないことがたくさんあります。ヤチボウズの断面についても、ヤチボウズを手当たりしだいに割ってみるわけにもいかないので、少ない例から推察することしかできません。博物館のレプリカの断面については、このような断面の個体もいるかもしれないけれど、サイズから推察すると実際とは違うんじゃないかな? と現時点では考えています。
(釧路市立博物館 学芸員 加藤ゆき恵)
引用
田中瑞穂. 1975.釧路湿原の植生. 釧路湿原総合調査報告書, p107-160. 釧路市立郷土博物館, 釧路.
ヤチボウズについてはこちらのコラムもご覧ください。
開拓を見つめ続けたヤチボウズ 【コラムリレー:北海道150年、学芸員にはどう見える?】
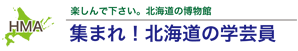 集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ
集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ









