浦幌町立博物館の常設展示室には、「聞かせてください、あなたのコロナ時代」という展示があります。2020年から現在まで続いているコロナ禍は、私たちの暮らしにさまざまな変化を及ぼしました。その変化を記録するには、時間が経ってしまってからでは収集できない消耗品資料があり、それらの資料を収集するための呼びかけとともに、モノとしては収集できない「声」をも収集しようという取り組みです。
コロナ禍を記録する資料のことを、当館では「コロナ関係資料」と呼んでいます。代表的なコロナ関係資料にマスクがあります。
もともとマスクは、衛生用品というよりも、鉱山や工場での煤煙から身を守るための保安用品でした。写真は、昭和初期、はじめてマスクが国産となった頃の資料です。表から見ると、色が黒いことがわかります。
このマスクのウラを見てみましょう。裏面は白いことがわかります。
そして、口を宛てるところには、穴の開いたセルロイド板が張られていました。セルロイド以前には、金網が張られていることもあったと言います。
小さなガーゼもあてがわれていました。この資料が大正時代末期のものか昭和初期のものか判断がつきかねていたのですが、ガーゼの国産化が昭和に入ってからなので、昭和初期の使用品だと判断することができました。
2020年2月、北海道が独自の緊急事態宣言を発布し、コロナ禍に関する緊張度が一気に増して、店頭からマスクが姿を消し、人々はマスクの手作りを始めます。
写真は浦幌町のある人が、良い布が手に入らず、自宅にあった浴衣を裂いて、マスクを初めて手作りしたものです。
上段が表面、下段が裏面です。表も裏もほとんど変わらないのがわかります。とりあえず口をあてられるように四角くしただけの簡素なものでした。
また、マスクにはガーゼが必要ということも最初は知りませんでした。気づいたところで、品切れでガーゼが手に入りませんでした。
そこで、キッチンペーパーを四角くたたみ、生地の間に挟んで代用としました。
こちらは、夫の古いワイシャツを切り裂いて作られたマスクです。形状が進化し、花の部分を高くするなど、マスクらしい形状に進化しましたが、まだゴム紐が手に入らず、ストッキングを細く裂いて代用としました。一方、ガーゼが手に入るようになり、裏面にあてがわれているのがわかります。
21世紀も20年も経過した日本で、マスクひとつ作ろうにも満足に材料が手に入らない、そうした物資不足の時期が存在したのでした。そのとき手作りされたマスクの変化を見ると、急迫した状況のなかで、人々が必死で工夫を凝らして乗り越えていたことがわかります。
マスクひとつにも、時代の大きな変化に対応しようとした人々の生き様が記録されます。同時代資料の収集には、さまざまな課題もありますが、その時代に意識して集めておかなければ消えてしまう消耗品のなかにも、時代の記録性が確かにあることを実感しました。
(浦幌町立博物館 学芸員 持田 誠)
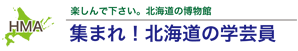 集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ
集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ










