コラムリレー08「博物館〜資料のウラ側」第1回
博物館の展示室。そこでは化石や土器、古文書や剥製など、いろいろな資料を見ることができます。
しかし、その裏側・内側にも数多くの情報が秘められていること、展示室の裏側ではさまざまな舞台裏の仕事があることを、ご存じでしょうか?
ふだんは見えない展示資料の裏側をちょっと覗いて、隠れたメッセージを読み取ってみましょう。
* * * * * * * * * * * * * * *
今から800万年前の二枚貝の化石。いしかり砂丘の風資料館で展示しているこの化石を、裏返してみると…。
いつもは下になっていた側の殻をよく見ると、そこには直径3mmの円い穴がありました。
札幌のすぐ北、石狩湾に面した石狩市望来(もうらい)海岸の地層からは、約800万年前の貝化石がたくさん見つかります。人類の祖先がアフリカに出現する少し前のこと、深い海の底に生息していた、ワタゾコウリガイと呼ばれる長さ4-5cmの二枚貝です。
穴が空いているのは、貝殻の表面だけ。殻の中には泥岩が詰まっていますが、穴からのぞいている泥岩は、まったく凹んでいません。ということは、現代人が空けた穴ではなく、800万年前、その二枚貝が生きていた時代に空けられた穴、ということがわかります。
貝に穴が空いた? なぜ? 空けたのはだれ?
——The present is the key to the past.——
(現在は過去を解く鍵である)
地球や生命の歴史を研究する地質学には、こんな言葉があります。
火山の噴火、海岸の波など、地層や化石に刻まれた太古の地球のできごとは、たとえそれが数百万年前、数億年前だろうと、現在と同じ自然法則で、今も見られる現象が起きていただけ——。
現在の自然界で見られることをヒントにすれば、地層や化石が秘めているメッセージを読み解くことができる、という地質学の大原則です。
それでは貝化石の穴は、いったい何なのでしょう?
その“鍵”を探しに、西暦2025年の海岸を歩いてみましょうか。
* * * * * * * * * * * * * * *
砂浜で貝殻を拾っていくと、けっこうな割合で穴の空いた二枚貝があるのに気づくと思います。きれいな円い穴なので、人間が空けたものだと思うかもしれませんが、そうではありません。実はこれは、二枚貝の中身が食べられた痕なのです。食べたのは誰かというと、肉食性の巻貝です。
ツメタガイなどタマガイ科の巻貝は、アサリやウバガイ(ホッキ貝)など二枚貝が好物です。獲物を見つけると静かに覆い被さり、口にある「歯舌」(しぜつ)と呼ばれるヤスリのような器官で、ガリガリとドリルのように穴を空け、チュルチュルと中身を食べてしまうのです。砂浜で見つかる穴の空いた二枚貝はすべて、タマガイ類に食べられた“被害者の遺体”だったのです。
800万年前の化石の殻の穴もこれとまったく同じ。同時代に生きていた巻貝に食べられてしまった痕なのです。
現代の二枚貝の穴をよく見ると、空けかたにもいろいろあるのがわかります。穴が貫通していないものや、1つの貝殻に穴が2つ空いているものも。ツメタガイに上から覆いかぶされ、ガリガリと削られながらも必死で逃れるコタマガイ。“もうダメか…”というところで辛うじて逃げ出せた者もいれば、一度はうまく逃げられたけどまた捕まってしまい、とうとう食べられてしまった者も。きっと800万年前の望来の海底でも、同じ闘いが何度も何度も繰り返されてきたでしょう。
800万年前の貝化石。ただの石コロじゃありません。裏返してみると、食わせろ、食われてたまるか、と命をかけて闘う生き物の姿が見えてくるでしょう?
<いしかり砂丘の風資料館 学芸員 志賀健司>



* * * * * * * * * * * * * * *
北海道内各地の学芸員たちが毎週交代で執筆する、コラムリレー。第8シーズンは“資料の裏側”がテーマです。2026年2月まで1年間、web連載します。
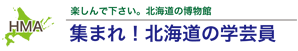 集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ
集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ







