名刺から鉄道車両まで
有島記念館は、有島武郎(1878-1923)という小説家が、北海道ニセコ町に所有した農場跡にあります。有島や農場の紹介だけではなく、ニセコエリアの郷土資料や、文学資料、美術作品を収蔵・展示しています。収蔵資料の幅広さは「最小は有島武郎の名刺から、最大は鉄道車両まで」です。
ニセコエクスプレスとは
ここでは、当館最大の収蔵資料「ニセコエクスプレス[キハ183-5001号(収蔵番号500001)]」(以下、同車)【写真1】保存のウラ側を紹介します。

同車は1988年、JR北海道苗穂工場(札幌)で誕生した、鉄道車両には珍しい「道産子」です。3両編成のリゾート列車で、千歳空港に着いた道外スキーヤーをニセコのスキー場へと高速かつ快適に輸送しました。2018年に老朽化のため引退し、全車解体予定でしたが、有志がニセコの名前を冠し、町の観光に貢献した車両を保存したいとクラウドファンディングを実施。全国の皆様から1千万円超の資金を頂戴し、先頭車1両が「ニセコ鉄道遺産群」【写真2】に保存されました。

末長い「保存」の裏側―お金のことなど
博物館がモノを保存するって、お金と責任が伴います。
学芸職員が調査研究の結果、収蔵に値すると判断したものを最良の状態で未来永劫、保存します。これは鉄道車両でも、文学資料でも、美術作品でもかわりません。 永久保存ですから、将来世代に保存コストの負担をかけ続けます。当館では収蔵車庫を建ることで、年間の維持管理経費を10万円程度に抑えました。

破損を考慮し、予備部品も確保しています【写真4】。再塗装に備えて塗料の記録、鉄道特有の文字、ロゴ類を譲渡頂き、それを型にして複製できるようにしてあります【写真5】。最近、鉄道車両はアルミ製などの無塗装が多数派です。その観点で、同車は鉄道車両工場塗装職場の仕事を残すため、屋外公開は極力控えています。


「車両」だけの保存でよいのか―資料価値を高めるために
学芸員が何をもって収蔵価値があると判断したか。その判断には車両と関連する資料も収集します。例えば、車両製造に使用した図面や整備記録の収集、設計や製作に携わった方の証言も記録しています。
スキーリゾート列車が誕生した80年代の熱狂的スキーブームという社会現象を伝えるため、当時のスキー板やウェア、旅行会社チラシなども収集対象です。
また、ニセコ町の学芸員は次世代にこんなも伝えられると考えました。この車両と関連資料(モノ)を通して、明治時代、町が鉄道開通により一大農業生産地として発展したこと、戦前から登山、スキーなど鉄道会社と協働で誘客をしたことが実を結び、今の国際リゾート地ニセコに成長したことを語り継げるのではないかと。それは同車の将来的な歴史的価値を高めることにもつながります。
なお、この車両のオリジナリティは車体や内装形状にあり、台車やエンジンは汎用品なことから、図面は車体分のみの収蔵ですし、車体保護のためにも動態保存は行いません。
最後に
博物館で保存される鉄道車両でも、これが「収蔵資料」なのかと愕然とする荒廃した車両に出会うこともあります。巨大ゆえか、なぜ館内収蔵庫に保存されている資料と同じように扱われないのか。
デジタル化が進めば博物館が集めるモノは限られるでしょう。鉄道車両のような巨大なモノこそ、個人では難しい、社会インフラとしての博物館が保存を担うにふさわしい資料になるかもしれないのに。
「ウラ方」の学芸員の調査研究対象はモノ自体にとどまりません。将来世代へコストを極力負わせない工夫はないか、保存にふさわしい設備とは、その財源なども研究対象です。頭が痛い日々が続きます。 (有島記念館 伊藤大介)
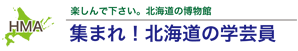 集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ
集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ





